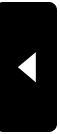お城ウンチク(松江城・萩城)
ブロガー魂地元(臼杵の名勝地)国宝の5城(NTC5)GT(現存天守)の12城大阪城姫路城中国の城松江城萩城豊後(大分)の城臼杵城
(はじめに)超長いので^^;城好き以外の方はスルー推奨!(爆)

戦国時代好き・・・の理由は様々ありますが^^;
その中でもお城!大好きです・・(笑)
お城って、天守櫓ばかり目が行きがちですがww
本来の「防御」や「籠城」に備えた「縄張り」がどうなってる?とか~
この堀はすごい!とか~高石垣が見事!とか~・・ま、全て好きなんです(笑)

だから?石垣だけの城もとっても見ごたえあります(笑)
でもね・・?

もちろん!400年以上の年月、風雪や地震に耐えてきた石垣技術も感動しますが~?
古写真なんかを見ると・・・やはり「日本建築技術の最高峰」である高層の「天守櫓」を見るとww
断然!・・・城は天守あったほうがいいな~って^^;

戦国の世が終わり・・秀吉のあと、家康は幕府の維持政策の一環で「一国一城令」を出します。
戦国の世がピークだった全国の城(天守がないものが多数)は約3000ほどあったらしいのですが・・
ここで一気に170くらいに激減します(´Д`;)

以後、泰平の世と言われる江戸時代が続き、各地の城は更に減少・・そして明治維新の内戦によって
多くの城が失われて・・・(--;)
今現在は、当時の建築で現存してると言われる城は12城に・・( 」´0`)」
そのうち?国宝とされている城が~

姫路城と

松本城、そして

彦根城、それから

犬山城、最後に

今回の松江城・・・国宝に指定されると別に文化財として文化庁から全て補修費用が出されてる訳ではなく
基本的には地方自治体や所有者が払うようですね^^;

ただ、松本城や姫路城などは「旧国宝」という現在の文化財保護法の国宝指定より前から
国宝であったので何回も大小の修理が行われて来ました・・。

江戸時代の修理に関しては資料が乏しく、記録のある明治では松本城は8割が寄付、姫路城の昭和の大修理
は一旦解体して組み直す「昭和の築城」と言われるほど大修理で約5億3,000万円、のべ25万人の人員と
様々合計すれば、約10億円(1964年当時の価格)に相当すると考えられています。

平成では、屋根修理が「平成の修理」として2009年(平成21年)6月から2015年(平成27年)3月にかけて行われました。
総事業費は約28億円(素屋根工事費12億6千万円、補修工事費15億4千万円)・・ここで画期的だったのが?

修復作業を公開して見れたこと(笑)普通なら、ドローンでもない限り(姫路城は飛行禁止)絶対見れない天守瓦などを
間近に見ることができました!・・行けなかったけど( ;∀;)

そこで起きた・・・「熊本地震」
震源に近かった熊本城は大被害を受けました・・。
ま、行かれた事ある方や~知ってる方は知ってますが・・?

熊本城は「現存建築」ではなく「外観復元」。
今回の地震で・・奇しくもこの写真で・・・(´Д`;)

コンクリート構造であることが確認できましたね( ;∀;)
このように・・・頑丈なコンクリート製でも大打撃を受けるのに・??
「木造復元」や「現存建築12城」は大丈夫なのか??・・ってなりますわな?( 」´0`)」

そこから数年かけて「耐震強度調査」が行われて~今年より各城で耐震工事が施工されてます。
今回行った松江城は運良く天守の最上階まで上れましたが~これより先は公開中断の城もあります(汗)
このように、現存建築は素晴らしい技術の継承であると同時に・・大変な手間と費用によって支えられているのですね^^;

そもそも・・木造でこのような高層な建築をする技術はすごいでしょ?^^;
姫路城がその最高峰で31.5m。次に松本城で25m。そして!今回の松江は3位の約22.4m!やっぱデカかった^^;
一般的に城のタイプは・・・

望楼型と言われるものは1階、または2階の入母屋造りの家屋の上に2~3階の望楼(物見)を載せたもの
層塔型は基部に入母屋造りの大屋根を持たず、単純に積み上げていくだけの構造と見分けるようです・・が?

層塔型の代表のような松本城や・・?

大きな入母屋破風のない、ただいま木造復元でもめてる^^;名古屋城なんかはなんとなくわかるのですが・・?
姫路城・・望楼なの?

こうやって分けてみると・・確かに入母屋に望楼が乗っかてる?(笑)
コンパクトでわかりやすい「望楼型の現存」としては・・

犬山城が有名ですね♪

これは望楼の代表格「豊臣大坂城」(左)と、層塔の代表格「江戸城」(右)の大きさ比較ですが~
建設に技術のいる望楼型に対して、層塔型はコストも安く高い建造が可能と言われてます(笑)
そんな中で、松江は立派な建築・・特に千鳥の大きな破風が見事でしたね~♪

この技術もいる贅沢な建築は、城に天守・・しかも、その天守に住むという行為も
信長の安土城が最初(諸説あり)と言われてます・・。

天下を手中に収めた権力の象徴!・・として、豪華絢爛に作られたとされる安土城。

戦において、高い位置から見下ろすというのは当然ですが^^;
やっぱ・・人は権力を持つと「高いとこに住みたがる」のかもね・・(爆)
その流れをさらに発展させた秀吉の・・・

*写真は現在の大阪城
巨大な堀や城下町をも取り込んだ大城郭の惣構の「豊臣大坂城」(爆)
以後、多くの大名がその城の縄張りや、城下町整備を行ってきました

この織田信長、豊臣秀吉の名からとって「織豊系城郭」と呼ばれてます。
私の好きな「熊本城」も、今回の「松江城」もこのタイプ♪

城下に武士の町や町人,商人の町など作り住ませて・・・大群の侵入を路地や建物で防ぐ・・

さらに内側川や水堀を設けて・・
高石垣や櫓、枡形路地や様々な仕掛けで侵入してくる敵を攻撃する・・。
本当に城って面白いo(^▽^)o

さて・・お次は「萩城」
これはCGで天守などを再現した様子ですが・・

この城の築城主こそ・・豊臣政権化でも大老、中国地方を制した毛利家!
関ヶ原の開戦前の領土は120万石の大大名でしたが・・・

関ヶ原での毛利家当主、輝元の行動については諸説ありますが^^;
結局、家康からは逆心ありと判断され長門・周防2カ国への減封にてやってきて・・
既存の山城では不便、日本海の海運も使うべく現在の萩に城を築城しました。
でも、この当時のここは・・?

このような島?のような小山に築城・・
古地図でも?

このように・・・(笑)
現在は埋め立て?られてる以前はこんな感じだったのではと?^^;

この・・ちょっと変わった構造?
手前には堀や石垣・・奥には詰城、周りは・・海に面してる?
平城?山城(詰城が)?、海城?・・・・
どっかで・・見たぞ?^^;

この古地図・・・(笑)
そう!俺が城好きになった要因の一つ!

戦国武将、大友宗麟が我が臼杵に作った天然の要害、丹生島城!にそっくり??^^;
ま、ちゅ~ても?

我が臼杵藩はせいぜい5万石?程度ww
天守櫓も3層だったと言われてますが~^^;

こちらは長州藩(萩藩?)は、腐っても2カ国40万石もある大国の居城・・・^^;
ほんとに立派でしたね♪
さあ、次はいつ?
どの城に行こうかな~♪
終わり

戦国時代好き・・・の理由は様々ありますが^^;
その中でもお城!大好きです・・(笑)
お城って、天守櫓ばかり目が行きがちですがww
本来の「防御」や「籠城」に備えた「縄張り」がどうなってる?とか~
この堀はすごい!とか~高石垣が見事!とか~・・ま、全て好きなんです(笑)

だから?石垣だけの城もとっても見ごたえあります(笑)
でもね・・?

もちろん!400年以上の年月、風雪や地震に耐えてきた石垣技術も感動しますが~?
古写真なんかを見ると・・・やはり「日本建築技術の最高峰」である高層の「天守櫓」を見るとww
断然!・・・城は天守あったほうがいいな~って^^;

戦国の世が終わり・・秀吉のあと、家康は幕府の維持政策の一環で「一国一城令」を出します。
戦国の世がピークだった全国の城(天守がないものが多数)は約3000ほどあったらしいのですが・・
ここで一気に170くらいに激減します(´Д`;)

以後、泰平の世と言われる江戸時代が続き、各地の城は更に減少・・そして明治維新の内戦によって
多くの城が失われて・・・(--;)
今現在は、当時の建築で現存してると言われる城は12城に・・( 」´0`)」
そのうち?国宝とされている城が~

姫路城と

松本城、そして

彦根城、それから

犬山城、最後に

今回の松江城・・・国宝に指定されると別に文化財として文化庁から全て補修費用が出されてる訳ではなく
基本的には地方自治体や所有者が払うようですね^^;

ただ、松本城や姫路城などは「旧国宝」という現在の文化財保護法の国宝指定より前から
国宝であったので何回も大小の修理が行われて来ました・・。

江戸時代の修理に関しては資料が乏しく、記録のある明治では松本城は8割が寄付、姫路城の昭和の大修理
は一旦解体して組み直す「昭和の築城」と言われるほど大修理で約5億3,000万円、のべ25万人の人員と
様々合計すれば、約10億円(1964年当時の価格)に相当すると考えられています。

平成では、屋根修理が「平成の修理」として2009年(平成21年)6月から2015年(平成27年)3月にかけて行われました。
総事業費は約28億円(素屋根工事費12億6千万円、補修工事費15億4千万円)・・ここで画期的だったのが?

修復作業を公開して見れたこと(笑)普通なら、ドローンでもない限り(姫路城は飛行禁止)絶対見れない天守瓦などを
間近に見ることができました!・・行けなかったけど( ;∀;)

そこで起きた・・・「熊本地震」
震源に近かった熊本城は大被害を受けました・・。
ま、行かれた事ある方や~知ってる方は知ってますが・・?

熊本城は「現存建築」ではなく「外観復元」。
今回の地震で・・奇しくもこの写真で・・・(´Д`;)

コンクリート構造であることが確認できましたね( ;∀;)
このように・・・頑丈なコンクリート製でも大打撃を受けるのに・??
「木造復元」や「現存建築12城」は大丈夫なのか??・・ってなりますわな?( 」´0`)」

そこから数年かけて「耐震強度調査」が行われて~今年より各城で耐震工事が施工されてます。
今回行った松江城は運良く天守の最上階まで上れましたが~これより先は公開中断の城もあります(汗)
このように、現存建築は素晴らしい技術の継承であると同時に・・大変な手間と費用によって支えられているのですね^^;

そもそも・・木造でこのような高層な建築をする技術はすごいでしょ?^^;
姫路城がその最高峰で31.5m。次に松本城で25m。そして!今回の松江は3位の約22.4m!やっぱデカかった^^;
一般的に城のタイプは・・・

望楼型と言われるものは1階、または2階の入母屋造りの家屋の上に2~3階の望楼(物見)を載せたもの
層塔型は基部に入母屋造りの大屋根を持たず、単純に積み上げていくだけの構造と見分けるようです・・が?

層塔型の代表のような松本城や・・?

大きな入母屋破風のない、ただいま木造復元でもめてる^^;名古屋城なんかはなんとなくわかるのですが・・?
姫路城・・望楼なの?

こうやって分けてみると・・確かに入母屋に望楼が乗っかてる?(笑)
コンパクトでわかりやすい「望楼型の現存」としては・・

犬山城が有名ですね♪

これは望楼の代表格「豊臣大坂城」(左)と、層塔の代表格「江戸城」(右)の大きさ比較ですが~
建設に技術のいる望楼型に対して、層塔型はコストも安く高い建造が可能と言われてます(笑)
そんな中で、松江は立派な建築・・特に千鳥の大きな破風が見事でしたね~♪

この技術もいる贅沢な建築は、城に天守・・しかも、その天守に住むという行為も
信長の安土城が最初(諸説あり)と言われてます・・。

天下を手中に収めた権力の象徴!・・として、豪華絢爛に作られたとされる安土城。

戦において、高い位置から見下ろすというのは当然ですが^^;
やっぱ・・人は権力を持つと「高いとこに住みたがる」のかもね・・(爆)
その流れをさらに発展させた秀吉の・・・

*写真は現在の大阪城
巨大な堀や城下町をも取り込んだ大城郭の惣構の「豊臣大坂城」(爆)
以後、多くの大名がその城の縄張りや、城下町整備を行ってきました

この織田信長、豊臣秀吉の名からとって「織豊系城郭」と呼ばれてます。
私の好きな「熊本城」も、今回の「松江城」もこのタイプ♪

城下に武士の町や町人,商人の町など作り住ませて・・・大群の侵入を路地や建物で防ぐ・・

さらに内側川や水堀を設けて・・
高石垣や櫓、枡形路地や様々な仕掛けで侵入してくる敵を攻撃する・・。
本当に城って面白いo(^▽^)o

さて・・お次は「萩城」
これはCGで天守などを再現した様子ですが・・

この城の築城主こそ・・豊臣政権化でも大老、中国地方を制した毛利家!
関ヶ原の開戦前の領土は120万石の大大名でしたが・・・

関ヶ原での毛利家当主、輝元の行動については諸説ありますが^^;
結局、家康からは逆心ありと判断され長門・周防2カ国への減封にてやってきて・・
既存の山城では不便、日本海の海運も使うべく現在の萩に城を築城しました。
でも、この当時のここは・・?

このような島?のような小山に築城・・
古地図でも?

このように・・・(笑)
現在は埋め立て?られてる以前はこんな感じだったのではと?^^;

この・・ちょっと変わった構造?
手前には堀や石垣・・奥には詰城、周りは・・海に面してる?
平城?山城(詰城が)?、海城?・・・・
どっかで・・見たぞ?^^;

この古地図・・・(笑)
そう!俺が城好きになった要因の一つ!

戦国武将、大友宗麟が我が臼杵に作った天然の要害、丹生島城!にそっくり??^^;
ま、ちゅ~ても?

我が臼杵藩はせいぜい5万石?程度ww
天守櫓も3層だったと言われてますが~^^;

こちらは長州藩(萩藩?)は、腐っても2カ国40万石もある大国の居城・・・^^;
ほんとに立派でしたね♪
さあ、次はいつ?
どの城に行こうかな~♪
終わり